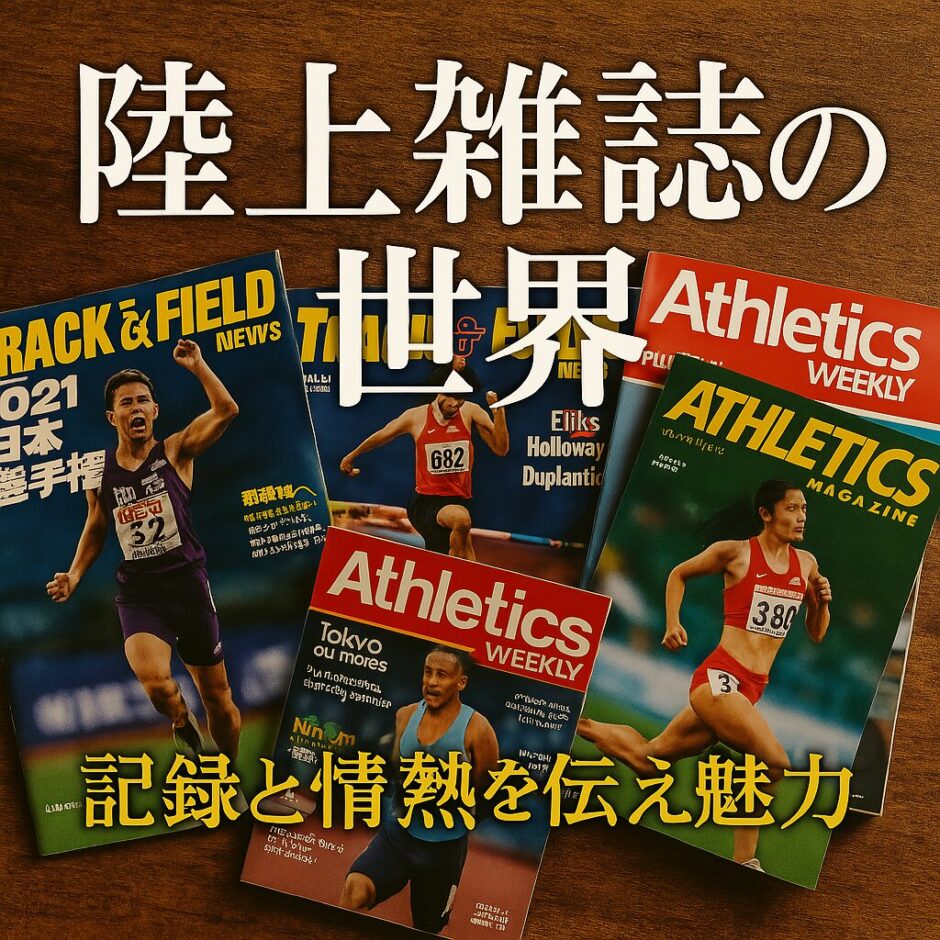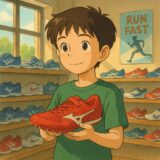Contents
はじめに|記録の先にある「感動」を届ける存在
100分の1秒を争う世界において、“文字”や“写真”はどこまで価値があるのだろうか。 速さを語るのは数字だ。 けれど、そこに至るまでのドラマを語れるのは「雑誌」だけだと思う。
スパイクの音、スタート前の呼吸、涙のゴールライン── これらを言葉とビジュアルで閉じ込めた“紙の奇跡”こそ、陸上雑誌。
本記事では、そんな陸上雑誌の魅力、歴史、代表的なタイトル、そして時代とともに変化する雑誌文化を情緒たっぷりに紹介していく。
第1章|陸上雑誌の“始まり”と“魂”
日本で最も古く、今なお存在感を放つ雑誌といえば『月刊陸上競技』(講談社)。 創刊は1971年──まさに「高度経済成長」とともに、スポーツ文化が成熟していく時代。
それは、単なる競技記録の報告ではなく、選手の「内面」や「成長物語」にフォーカスし始めた時代でもあった。
特集記事の見出しはまるで詩のよう。 「風を追いかける少年」 「一歩の先に、夢があった」
こうした見出しの裏には、記者が現場で見た、聞いた、“震える瞬間”が詰まっている。
第2章|代表的な陸上雑誌たちとその個性
◼ 月刊陸上競技(講談社)
- 日本の“陸上文化”を支えてきた王道
- 大会速報、選手インタビュー、練習メニューまで網羅
- 「人に焦点を当てる力」が抜群
◼ 陸上競技マガジン(ベースボール・マガジン社)
- データと記録に強い
- 高校・中学の部活動層にも人気
- 巻頭特集の「陸上界の未来」シリーズがアツい
◼ 月刊Athlete(休刊)
- 陸上×人間ドラマの融合
- 表紙やレイアウトの美しさでファン多数
- アーカイブがプレミア化しているほどの人気
第3章|紙からデジタルへ──時代の流れと共に
2020年以降、雑誌は次々とデジタル移行を余儀なくされている。 『月刊陸上競技』もアプリ化し、スマホで読めるようになった。 しかし、そこには“紙でしか味わえない体温”が確かに存在していた。
ページをめくる音。 誌面のインクの匂い。 写真の余白に宿る静けさ。
デジタル化が進んでも、紙の雑誌が与えてくれる「体験」は決して色褪せない。
第4章|読者が“共犯者”になるコンテンツ
面白いのは、陸上雑誌の多くが「読者投稿コーナー」を持っていることだ。
- 『私の勝負スパイク』
- 『試合前のルーティン』
- 『応援してるこの選手が熱い!』
こうした声が誌面に掲載されることで、読者は“ただの観客”ではなく、“物語の共犯者”になる。
第5章|心を震わせた名特集たち
- 『ラストラン。あの日の背中を忘れない』
- 『この涙の意味を、君は知らない』
- 『人生を変えた、たった一度のスタートライン』
これらは、選手の引退特集や、復帰インタビュー、ケガからの再起を追った記事タイトルたち。 文字を読むだけで、走る姿が浮かぶような、“エモの極み”が詰まっている。
第6章|高校生アスリートと雑誌の関係
全国高校駅伝(都大路)前の選手紹介特集は、もはや“風物詩”。
- 学校紹介
- 注目選手プロフィール
- チームの戦術や練習風景
高校生にとって、「雑誌に載る」ことは一種の夢であり、誇りでもある。
掲載された誌面を切り抜いて、寮の壁に貼る選手たち。 仲間と一緒にコンビニでページをめくるその瞬間が、青春そのものだ。
第7章|これからの“陸上雑誌”に求められるもの
時代が変わり、AIが記事を書き、SNSが瞬間を拡散する世の中で、雑誌の存在意義とは何か。
答えはシンプルだ。
「記録に残らない“感情”を、記録する」
速報性では勝てないかもしれない。 けれど、心に残る特集は、10年後も読み返したくなる。 そういう“時間を超える力”が、雑誌にはある。
おわりに|ページをめくるたび、誰かの物語が始まる
陸上とは、走ること、跳ぶこと、投げること。 けれど、その先にある「想い」こそが、雑誌が紡いできたものだ。
一冊の中に、世界がある。 表紙をめくるその瞬間から、あなたはその世界の住人になる。
記録だけを追いかけるのではなく、 記録の“向こう側”を旅する。
そんな読書体験を、陸上雑誌は今も静かに提供し続けている。
次のページには、まだ見ぬ感動が待っているかもしれない──。
※この記事が気に入った方は、ぜひ『月刊陸上競技』『陸上競技マガジン』をチェックしてみてください。紙でもデジタルでも、“走る想い”が、そこにはあります。