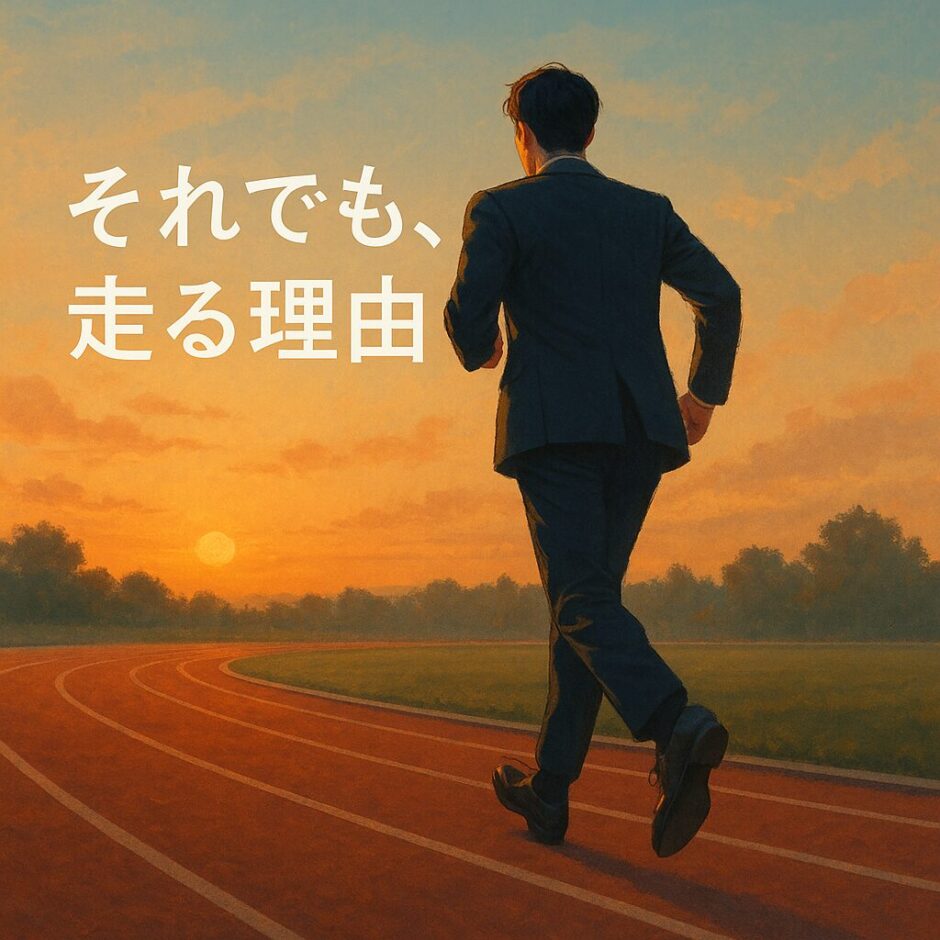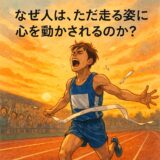Contents
序章:「走る時間がない」──それでも、走る人たちへ
朝7時、満員電車。
夜10時、仕事終わりのコンビニ前。
週末、家族サービスと付き合いの狭間で。
どこに“走る時間”があるのか?
社会人になって、陸上競技を続けることの難しさは、想像以上だ。
学生時代のように、放課後が自由に使えた日々はもうない。今は、タイムカードとにらめっこしながら、スパイクの代わりに革靴を履いている。
しかし、それでも走り続ける人たちがいる。
なぜ彼らは、そんなにも走り続けるのだろうか?
第1章:「走る」ことが、仕事以上に大切だった
ある社会人ランナーは語る。
「自分にとって陸上は、歯磨きみたいなもの。やらないと、気持ち悪いんです。」
1日30分、たった5kmでもいい。
走ることで心が整い、自分が“自分”に戻れる感覚がある。
それは数字では表せないし、成果主義のビジネス社会とは真逆の世界かもしれない。
だが、そうした“自分の芯”を失わないことが、実はビジネスの現場でも効いてくる。
走ることでリズムが整い、集中力が増し、メンタルも強くなる。
「趣味の陸上」が、仕事のパフォーマンスを支えている。
皮肉にも、最も“役に立たない”と思われがちな陸上が、最も“役に立つ”ものとなっているのだ。
第2章:最大の敵は「時間」ではない
社会人が陸上を続けるにあたって最大の敵は、「時間」ではない。
それは、「孤独」だ。
大学時代は仲間がいた。応援してくれる人がいた。
だが、社会人になると、多くの人が陸上を辞め、練習相手も減っていく。
会社では、「まだやってるの?」「もういい年だよ」などと、軽く見られることもある。
家族からは、「それって何の意味があるの?」と問われることもある。
孤独の中で走る。
誰に認められるわけでもなく、誰かの評価も得られない。
でも、それでもやる。やりたい。走りたい。
それが「本物の走る理由」なのかもしれない。
第3章:社会人だからこそ、“競技”が輝く瞬間がある
多くの市民ランナーやクラブチーム所属の選手たちが、全日本マスターズや都道府県選手権などに出場している。
彼らの笑顔は、本当に輝いている。
20代も、30代も、50代も、70代も。
「順位より、自分の記録を超えることが嬉しいんです。」
「勝つため」ではなく「生きるため」に走る姿が、そこにはある。
競技が人生のゴールではない。
けれど、競技を通して、人生が何倍も豊かになる。
第4章:どうすれば“続けられる”のか?
1. 練習環境を「ルーティン化」せよ
朝ランを習慣化している社会人は多い。通勤前に5km走るだけでも、身体は仕上がってくる。
「気合い」ではなく、「仕組み」で走るのが、社会人の鉄則。
2. SNSでつながれ
X(旧Twitter)やStrava、TATTAなどで、走る仲間を見つけよう。共感や刺激を受けられるコミュニティは、孤独を癒やしてくれる。
3. 目標設定は“ゆるく、深く”
ベスト更新ではなく、「月に100km」「大会で笑顔で走り切る」など、続けるための目標を持とう。
数字より、“心が動く目標”を。
結語:あなたの走りは、誰かの希望になる
仕事で疲れても、家庭でバタバタしても。
土日の1時間を、自分のために使う。
そんな姿を見て、誰かが「自分もやってみよう」と思うかもしれない。
社会人になっても陸上を続けるということは、
“走ることの本質”と、真っ向から向き合うことなのだ。
記録ではなく、継続を。
勝利ではなく、誠実を。
あなたの走りは、静かに誰かの人生を変えている。